内田百閒の短篇小説「棗の木」について
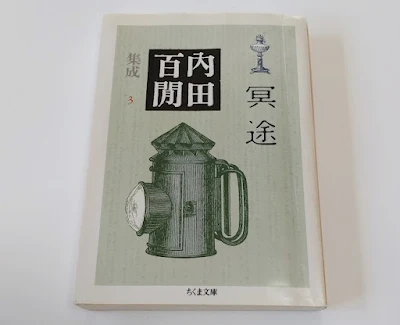 |
| 内田百閒集成3「冥途」 ちくま文庫 |
解説「文字と夢」
ちくま文庫・内田百閒集成3「冥途」の解説は、多和田葉子氏が書いておられる。「文字と夢」という題名がつけられた解説において、氏は、百閒の小説は「文字達がどれも妙に生き生きとして見えてくる」と述べている。
その例として「件」や「蜥蜴」や「道連」などをあげている。
たとえば「件」は、「人」と「牛」から成り立っていて、その文字の形が「件」という物語の象徴となっているのではという氏の示唆が感じられる。
「道連」という物語では、タイトルの漢字に部首であるシンニョウがふたつ続いており、片方のシンニョウが「私」で、もうひとつのシンニョウが、「私」の「生まれなかった兄」を表しているのではないか、とか。
そういう多和田葉子氏は、この集成3に収録されている「棗(なつめ)の木」には一言もふれていない。
「棗」という文字も、朿(とげ)が上下に重なっていて面白い。
この文字の陰に、多和田氏がいうところの、百閒の「洒落」が潜んでいるような気がするのだが。
「私」と古賀
それは、ともかく。短篇小説「棗の木」は、「私」と高利貸しの古賀との、高額な利子の返済をめぐる攻防の物語である。
「私」と古賀とのやりとりでの、「私」の微細に揺れ動く心境が描かれている。
「私」という人物は、長い間の借金生活で苦心した作者(内田百閒)自身を彷彿させる。
作中では、「御座んせんよ」が口癖の古賀という男の人物像が際立っているのが印象的だった。
登場人物の中で古賀だけが突出していて、「私」は古賀の陰に隠れて古賀ほどの存在感がない。
「私」は、古賀を恐れながらも、古賀の徹底した取立てぶりに好感を抱いているという感情の持ち主である。
読者は、気弱で、いささか自虐的な「私」に、物足りなさを感じるかもしれない。
「私」は、物語の語り手であり、おおぜいの高利貸しから高額な利子の支払いを迫られている生活者であり、陸軍関係の官立学校に勤めている教官(おそらく語学の)である。
その官立学校も、古賀が俸給を差し押さえるという手段をとったために辞職することになる。
そんな物語のあらすじが一章に書かれている。
微妙な違い
二章から五章までは、一章に書かれたあらすじに沿って、「私」と古賀との顛末が描かれている。そして最終章である六章では、一章と同じ場所である古賀の家のなかでの、「私」と古賀との対話で物語が締められている。
この小説を読み終えて気になったことは、始まりの一章と終わりの六章が同日同時刻なのかということ。
別の時間帯であるように感じるのは、文章の雰囲気が微妙に違うせいだろうか。
棗の木の不安な陰
「庭に一本棗の木がある」で一章は始まっている。古賀の家を訪問した「私」が、庭の棗の木を見た感想が語られている。
障子に嵌めた硝子越しに見える寒寒とした日向を受けて、枝も幹も丸裸の荒い影を、向こうの板塀の裏側に落としている。これ以後「棗の木」は登場しない。
最終章で繰り返される一章のキーワードは「翻訳」と「天供閑日月」だけ。
類語的には一章の「大学を出ていなさる」に相当する言葉として、最終章の「ご立派な方」を並べることができる程度である。
最終章が一章の継続だとして、小説のタイトルでもある「棗の木」の再登場を期待して読み進めたが、この意味ありげな「棗の木」は姿を現さなかった。
「棗の木」は、物語から忽然と姿を消すのである。
ただ、残像のように、棗の木の不安な陰が作中に見え隠れする。
それは、大地震の焼け跡の陰だったり、俸給差押による貧困の陰だったり、調停裁判所の壁際に並んだ腰掛けの周辺の暗い陰だったり。
どこかとげとげしさがむき出している印象を感じる。
現在と回想シーン
ここで、小説「棗の木」についての、私の拙い読み方を記しておこう。この小説は一章から六章までに区切られているが、「私」という語り手が「小説上の現在」を語っているのは六章であると感じている。
一章から五章までは、「私」の回想シーンであると思える。
六章には、回想シーンにあるような緊張感は感じられない。
「私」と古賀の対話は、意外にも和気あいあいとしたものになっている。
一緒にお酒を飲む話まで出てくる。
「私」の社会的地位を根底から破壊してしまった古賀の面影は、六章では消えている。
これが、私が感じている微妙な雰囲気の違いである。
棗の木が表しているもの
「枝も幹も丸裸の荒い影」は、あきらかに、借金で貧乏をしている「私」のイメージである。とすれば、「私」をそういう影にしているところの「棗の木」は、古賀ということになる。
棗の木は、実がつき始めると害虫が発生しやすくなることで知られている。
「私」の暮らし向きが整いかけると害虫のような高利貸しが群がってくる。
そういうことであれば、「棗の木」は「私」を表しているとも読み取れる。
不安と安堵
この物語は、古賀の言ったことに対して「私」が「合槌を打った」というところで閉じられている。「棗の木」が「私」であれ古賀であれ、「私」が古賀に「合槌を打った」とき、イメージとしての「棗の木」は両者の影ではなくなったように思われる。
小説の冒頭で、物語を象徴するような「棗の木」の不安なイメージを出現させ、最後に、そのイメージを登場人物の暗い陰とともに霧消させる。
暗い霧が晴れたような安堵感。
不安と安堵の陰影。
「あの本は売れましたね」と「私」が合槌を打ったとき、「私」の暮らしに少し光が射したような。
そういう風に読んだら、物語の空間に、微妙な陰影が見え隠れしているように感じた。
もしこの小説の読者が、棗の木の「荒い影」に不安な陰を感じたら、その不安は、最終章まで消えることはないだろう。
「私」が合槌を打ったときに、ようやく不安が安堵に変わる。
最後に
最後に、棗の文字に潜んでいるものは何だったのだろう。何かが潜んでいたのか、いなかったのか。
それは不明のまま、読了してしまった。
色文字部分:小説からの抜粋
参考文献:ちくま文庫 内田百閒集成3 「冥途」内「棗の木」と解説「文字と夢」
参考文献:ちくま文庫 内田百閒集成3 「冥途」内「棗の木」と解説「文字と夢」



