秋十とせ却って江戸を指す故郷
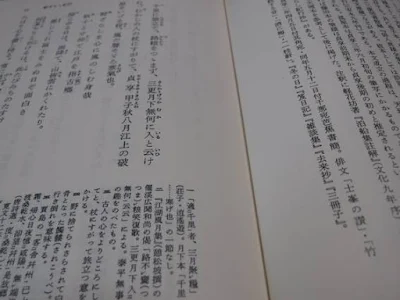 |
| 【芭蕉紀行文集(岩波文庫)より「野ざらし紀行」の頁。】 |
「野晒紀行」の旅
「芭蕉年譜大成(著:今榮蔵)」の貞享元年のページには、以下の記述がある。「貞享元年八月、芭蕉は初度の文学行脚に旅立つ。以後、生涯を終えるまでの十年の歳月の間に通計四年九箇月を旅に暮らす境涯に入る。」
この「初度の文学行脚」で芭蕉は、俳諧紀行文「野晒(のざらし)紀行」を著している。
芭蕉が「野晒紀行」の旅へ出発したのは、貞享元年八月の中旬頃とされている。
「旅人と我が名呼ばれん」という思いを、この頃すでに抱いていたのではあるまいか。
「野晒紀行」の旅の行程の概略は、以下の通り。
江戸深川から東海道経由で伊勢→伊賀上野→大和北葛城郡竹内村→吉野→山城・近江路→美濃大垣→桑名→熱田→名古屋→伊賀再訪(越年)→奈良→京都→伏見→大津→水口→桑名再訪→熱田再訪→鳴海→甲斐→甲州街道経由で江戸帰着(貞享二年四月末頃)。
旅の同行者は、門人の苗村千里(なえむら ちり)。
芭蕉はこの旅で多くの土地を訪問し、多くの知己を得たとされている。
結果的に「蕉門」の地盤を築く旅になったのである。
芭蕉の年齢は、四十一歳から四十二歳の頃。
季節は、秋から翌年の初夏まで。
日数は、約八ヶ月半。
俳諧紀行文「野晒紀行」
「野晒紀行」の書き出しは、「千里に旅立(たびだち)、路糧(みちかて)をつゝまず、三更(さんこう)月下(げっか)無何(むか)に入(いる)と云(いひ)けむ、むかしの人の杖にすがりて、貞享(ぢようきょう)甲子(きのえね)秋八月江上の破屋をいづる程(ほど)、風の聲そゞろ寒氣也」となっている。芭蕉の俳諧紀行文の第一作が、この「野晒紀行」である。
以下は、私の下手な現代語訳。
「旅の携帯食を持たずに、千里の長い旅に出る。子の刻の月の下では、無我の境地に至ると言われている。そういう昔の人の言葉をよりどころにして、貞享“きのえね”の年の秋八月、川のほとりの草庵を出るにつれて、風の音がなんとなく寒々と聞こえる。」
「江上の破屋」とは、旅の詩人としての「風狂」的なイメージを、深川の芭蕉庵にかぶせようとしたのだろう。
「風の聲そゞろ寒氣也」は「この旅は困難なものになるであろう」という芭蕉の心境を吐露したもののように思われる。
この書き出しの後、芭蕉は、「野ざらしを心に風のしむ身哉」とつぶやく。
それは、劇を演じる旅人の台詞のようである。
この句を詠むことによって、芭蕉は旅の舞台に立ったのである。
そして続けて、もっと名調子な台詞を独白する。
あたかも観客に語りかけるように。
旅立ちの句
秋十(と)とせ却(かえ)って江戸を指(さ)す故郷これから故郷へ向けて江戸を旅立つ身だが、江戸で十回の秋を過ごした歳月を思うと、故郷は伊賀上野ではなくて、逆に江戸のような気がしてくるなあ。
という感慨を、旅の舞台で観客に向かって披露する。
観客とは、「初度の文学行脚」を見送る杉山杉風(すぎやま さんぷう)や李下(りか)ら門人たち。
やがては紀行文を読むであろう読者たち。
そして、その観客たち後ろには、旅人の行く末を見つめる芭蕉自身がいる。
これから書く紀行文の編者として、この旅の始終に目をこらしている芭蕉。
芭蕉は劇を演じ、その劇を見て「野晒紀行」を書いていたのかもしれない。
こうして冒頭部分にあげた旅の行程を、四十一~四十二歳の芭蕉が、秋から翌年の初夏へと約八ヶ月半かけて歩み続けたのであった。
ところで、上にあげた二句は、旅立ちの句として対をなしているように私には感じられる。
それは言ってみれば、「はじまり」と「おわり」である。
「野ざらしを心に風のしむ身哉」は、たとえ「野ざらし」になってもかまわないという決意を「心」に、寒風を「身」に受けて、旅に出発するという句。
一方、「秋十とせ却って江戸を指す故郷」の「却って」は「帰って」に掛けているように思われる。
「野ざらし」になってたまるものか、十数年過ごした故郷とも言える江戸を目指して、かならず帰って来るよ。
帰ってきて、この旅を成就させてみせる。
そういう決意の句のようにも感じられる。
不吉な言葉を口に出したら、それが現実になる。
【そういう考えが、芭蕉にあったかどうか・・・・。言葉の達人であった芭蕉は、誰よりも言葉を畏れていたのではあるまいか。】
とにかく、「野ざらし」はマイナス志向。
ここは、プラス志向の句をもうひとつ作って、プラマイゼロにしなければならない。
【そういう考えが、芭蕉にあったかどうか・・・・】
だが、出発そうそう無事帰着の句では、「野ざらし」の覚悟や意気込みにかっこうがつかない。
そこで、さらに調子をあげて「秋十とせ却って江戸を指す故郷」と体言止めの力強い句を詠む。
しかし、江戸を故郷と思って旅に出るぐらいのイメージでは、プラマイゼロにはならない。
プラマイゼロにするためには、「野ざらし」に続く句が「自己成就予言」でなければならない。
「却って」は、予想とは反対になるさまをあらわす言葉である。
「反対に」とか「逆に」という意味がある。
「逆を指す」とは、「野ざらし」に向かう方向を変えて「江戸を指す」ことにつながる。
さらに、「江戸」を「故郷」と想定し、かならず「故郷」に「却って>帰って」俳諧の旅を成就させようと、「秋十とせ却って江戸を指す故郷」の句を詠んだのではあるまいか。
「野ざらし」で「はじまり」、「江戸を指す故郷」で「おわり」である。
「おわり」を予言することで、人生はじめての長旅の成功を祈ったのである。
「野晒紀行」の旅で大垣に到着したとき、芭蕉は「死にもせぬ旅寝の果てよ秋の暮」という句を作っている。
その前文に「武蔵野を出づる時、野ざらしを心に思ひて旅立ちければ、」とある。
芭蕉は、「野ざらしを心に」の句を作った後、すぐに「秋十とせ却って江戸を指す故郷」を作って、縁起でもない思いを打ち消したのだった。
だが「野ざらし」のことが、旅の途上大垣あたりまでずっと頭に残っていたのかもしれない。
その思いを「死にもせぬ旅寝の果てよ秋の暮」ですっかり打ち消した。
この句でプラマイゼロどころか、プラスを獲得したという心境になったのではなかろうか。
お笑いめさるな、いつもの「トーシロ」の推測なのだよ。
ところで、芭蕉が江戸に出てきたのは、寛文十二年(1672年、二十九歳)の春であるから、貞享元年(1684年、四十一歳)は厳密に言うと「秋ととせあまりみとせ」となる。
念のために。
元禄七年(1694年)には「芭蕉翁甲子の紀行」、元禄十一年(1698年)には「芭蕉翁道乃紀」、正徳五年(1715年)には「草枕共野ざらし紀行共いふ」とある。
それが、明和五年(1768年)には「野ざらし紀行」、安永四年(1775年)には「野晒紀行」や「甲子吟行」となったという。
<このブログ内の関連記事>
◆見やすい! 松尾芭蕉年代順発句集へ
帰ってきて、この旅を成就させてみせる。
そういう決意の句のようにも感じられる。
プラマイゼロ
「野ざらし・・・・」と声に出したものの、「野ざらし」なんて縁起でもない。不吉な言葉を口に出したら、それが現実になる。
【そういう考えが、芭蕉にあったかどうか・・・・。言葉の達人であった芭蕉は、誰よりも言葉を畏れていたのではあるまいか。】
とにかく、「野ざらし」はマイナス志向。
ここは、プラス志向の句をもうひとつ作って、プラマイゼロにしなければならない。
【そういう考えが、芭蕉にあったかどうか・・・・】
だが、出発そうそう無事帰着の句では、「野ざらし」の覚悟や意気込みにかっこうがつかない。
そこで、さらに調子をあげて「秋十とせ却って江戸を指す故郷」と体言止めの力強い句を詠む。
しかし、江戸を故郷と思って旅に出るぐらいのイメージでは、プラマイゼロにはならない。
プラマイゼロにするためには、「野ざらし」に続く句が「自己成就予言」でなければならない。
「却って」は、予想とは反対になるさまをあらわす言葉である。
「反対に」とか「逆に」という意味がある。
「却って」で俳諧の旅の成就を願う
芭蕉は「却って」という言葉を使うことで、「野ざらし」とは「逆を指す」という呪文を念じたのである。「逆を指す」とは、「野ざらし」に向かう方向を変えて「江戸を指す」ことにつながる。
さらに、「江戸」を「故郷」と想定し、かならず「故郷」に「却って>帰って」俳諧の旅を成就させようと、「秋十とせ却って江戸を指す故郷」の句を詠んだのではあるまいか。
「野ざらし」で「はじまり」、「江戸を指す故郷」で「おわり」である。
「おわり」を予言することで、人生はじめての長旅の成功を祈ったのである。
「野晒紀行」の旅で大垣に到着したとき、芭蕉は「死にもせぬ旅寝の果てよ秋の暮」という句を作っている。
その前文に「武蔵野を出づる時、野ざらしを心に思ひて旅立ちければ、」とある。
芭蕉は、「野ざらしを心に」の句を作った後、すぐに「秋十とせ却って江戸を指す故郷」を作って、縁起でもない思いを打ち消したのだった。
だが「野ざらし」のことが、旅の途上大垣あたりまでずっと頭に残っていたのかもしれない。
その思いを「死にもせぬ旅寝の果てよ秋の暮」ですっかり打ち消した。
この句でプラマイゼロどころか、プラスを獲得したという心境になったのではなかろうか。
お笑いめさるな、いつもの「トーシロ」の推測なのだよ。
ところで、芭蕉が江戸に出てきたのは、寛文十二年(1672年、二十九歳)の春であるから、貞享元年(1684年、四十一歳)は厳密に言うと「秋ととせあまりみとせ」となる。
念のために。
「野晒紀行」の名称について
なお、「芭蕉紀行文集(岩波文庫、中村俊定校注)」によれば、「野ざらし紀行」は芭蕉自ら命名したものではないとのこと。元禄七年(1694年)には「芭蕉翁甲子の紀行」、元禄十一年(1698年)には「芭蕉翁道乃紀」、正徳五年(1715年)には「草枕共野ざらし紀行共いふ」とある。
それが、明和五年(1768年)には「野ざらし紀行」、安永四年(1775年)には「野晒紀行」や「甲子吟行」となったという。
<このブログ内の関連記事>
◆見やすい! 松尾芭蕉年代順発句集へ



